Contents
ダムは川の水量を一定する装置
水量を安定させるダム

バイオライトとモバイルバッテリーは川とダムのような関係です。
またいつもの脱線話にお付き合いください。
脱線話が不要な人は半分下へお進みください。
川は一年を通じて安定した水量があるわけではありません。
年間を通じて安定した雨量があるわけではないし、湧水だけで川を河口まで流すのは難しいと思うのです。
そこでダムです。
ダムで1年の貯水量が一定になる規模の水を貯水することで川の水量をコントロールします。
川の水が多ければダムからの水量を減らし、川の水が減ればダムからの水量を増やす。
たまにダムの水が溢れそうになり、放水という行動を取りますが、往々にして川の水をコントロールします。
ゴムボートが防災グッズ

友人がゴムボートと言った時はえっ?と聞き返してしまいました。防災なんて意識がなかった数十年前の話。
「必需品は?」と聞いて「ゴムボート」と答えていた友人がいます。
彼にとってはゴムボートが防災グッズなのです。
「ゴムボートがないと移動ができないから」だと。
何故なら毎年友人宅横の川が氾濫してたからです。
してたには続きがあります。

毎年秋になるとこんな映像が。台風とかじゃなくて予定通り、秋の恒例・風物詩という位置づけです。
そして数年後、別のグループで知り合った人と話をしていたら、川の仕事をしていると。
その方はゴムボートが防災グッズと呼んでた友人宅横の川の氾濫を止めた人だった。
ということを知った時にはご縁だなあと思いました。
川底を掘り、堤防を上げ、水量をコントロールして氾濫が止まった。
ただそれだけの話ですが、成し遂げるまで数十年。
災害なんてピンと来ない若造でも感動したのを覚えています。
今回のバイオライトも少しの発電をどう活かすかがポイントのウッドストーブです。
関係性はあると思います。
口が空いているならモバイルバッテリーを差す
バイライトは

ケトルの中に全て入ります
ミニ火力発電所的ウッドストーブです。
燃焼炉に背負う形で本体を取り付けます。
この本体には熱を電気に変える素子とバッテリー、燃焼炉に風を送るファン、電気をアウトプットするUSB-A端子で構成されています。

ケトル、燃焼炉、本体
自宅でバッテリーを充電することはできますが、我が家ではしたことがありません。
- なくても使用に問題がない
バイオライトはファンが回らないとうまく燃焼しないのでファンが回った方が良いのですが、バッテリーゼロでもファンが回るまで数分。 - 放電が早い
普段から充電していないからかもしれませんがバッテリーは不安定なので、現場で発電すれば良いという意識に変えています。

コンパクトな燃焼炉。上部には穴があり、ここから空気が入ります。二次燃焼のハシリです。
というのが理由なのですが、2が不安定なのと設計がやや古いのでバッテリー容量が足りないのです。
現代のスマホ1台をフル充電するのは厳しいです。
USBには何かしら繋ぐ

我が家では最初に繋いでしまいます。
バイオライトで燃やす時間は実質1〜2時間でしょう。
3時間使ったら灰の処理が必要になるので中断。
充電できるとは言え考えると案外タイトなのです。

結構豪快な燃えっぷり
そう考えるとUSBには何かしら繋いでおきたいものです。
参考までに我が家は、
- スマホ(充電)
- LEDランタン(ゴールゼロの充電が多いです)
- 標準ライト(これが光量光質共に良い)
- モバイルバッテリー(充電)
という優先順位で接続しています。
デイキャンプの場合はモバイルバッテリーを繋ぐことが多いです。
フル充電ならもちろん繋ぎません。

本体の充電量は気にせずモバイルバッテリーに充電します。
少しの電気も逃したくないという思いです。
火力発電は潤沢仕様ではありませんから。
モバイルバッテリーはダムに似ています。
電気をせき止め使いたい時に供給してくれます。
最近気に入っているスマホ充電器
最近、乗せるだけで充電できるスマホ充電器が気に入っています。
背が立つのでスマホスタンドとしても使えるからです。
時代ですねえ。
バイオライトのUSBは常に埋めておく、最終的にモバイルバッテリーを差しましょう!

時代は変わり今ではソーラーパネルの方が充電できるのかもしれません。
ですが、ソーラーパネルの大きさ、繋ぐポータブルバッテリーの大きさを考えると、難しい局面もまだまだ多いと思います。
そんな時にはバイオライト。
そしてモバイルバッテリーの組み合わせはまだまだ現役。
落ちている枝を使いお湯が沸かせ、発電できるバイオライト。
小学生でも親が監視のもとある程度は使いこなせます。
我が家ではまだまだ現役です。











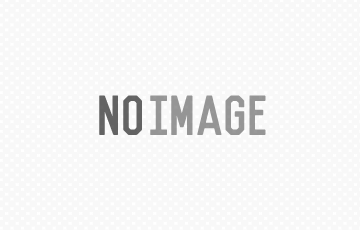














コメントを残す